白い象はそのとおりで、釈迦の誕生を祝う花祭りの時に山車のように使われることもあります。この風習は日本の各地に残っていますが、古くは中央アジアでも行われていたことが、玄奘の『大唐西域記』にも記されています。経典では釈迦は兜卒天(とそつてん)から白い象の姿をとって降りてきて、母親である摩耶夫人(まやぶにん)の胎内に入ったと記されています。先週お見せしたバールフットの浮彫はそのまま、象が摩耶夫人の上に浮かんでいます(このまま落ちてきたら、摩耶夫人はつぶれてしまいそうですが)。これに対し、中国では釈迦が象の姿をとるということに抵抗があったようで、象が乗り物のようになって、その上にお稚児さんのような釈迦がまたがった姿で描かれます。日本でもその伝統が受け継がれ、拓胎霊夢の作例では、たいてい象に乗った釈迦となっています。花祭りの白い象は、これを受け継ぐものでしょう。なお、普賢菩薩(ふげんぼさつ)という菩薩は象に乗ることがありますが、これも関係するかもしれません。象徴的な表現は、写実的な表現に比べると、たしかに作品の解釈や理解という点では劣るように見えるかもしれませんが、当時のインドの人々にとっては、必ずしもそうではないかもしれません。われわれは写真やテレビなどの映像に慣れているので、一見、本物のように見えることが、ありのままの姿のように思いますが、それ以前の人々にとって、絵とは必ずしもそのようなものに限りません。それは文化や嗜好によって大きく異なるでしょう。日本の江戸時代の浮世絵などもその一例です。あるいは、新聞で政治家などの有名人を写真ではなく、誇張気味の似顔絵で表現するのも、一種の象徴的な表現と見ることが可能です。絵画と「ありのままの姿」の関係は、これからも授業の中で取り上げて行くつもりです。
神のような崇高な存在を、自分たちと同じ人間の姿で表せないという考えは納得できたんですけど、だからって、なぜ木や法輪に象徴するか疑問です。万物に神が宿るという日本古来の考え(アニミズムでしたっけ?)に少し似ているのかなぁと思いました。
象徴的な表現として選ばれるものは、いずれも何らかの意味を持っています。たとえば、法輪は釈迦が説いた教えの象徴ですが、その背景には輪の持つ意味と、さらにそれを一種のエンブレムとする帝王観があります(これについては今回取り上げます)。樹木はインドでは古くから民間信仰の対象として、きわめて重要な意味があります。これは現在でもインドで広く見られ、樹木そのものが神と見なされ、礼拝されています。釈迦が生まれるときに、摩耶夫人が無憂樹という樹木につかまったり、釈迦が悟りを開くときに菩提樹の根本に坐ったり、涅槃にはいるとき、沙羅という2本の木の間で横たわったりしたのも、このような樹木崇拝と関係があるといわれています。とくに菩提樹は、悟りを開くために一種のエネルギー源のような役割を果たしたようで、釈迦の悟りと密接に結びついています。このほか、足跡や仏塔なども釈迦のかわりにシンボルとして用いられます。「万物に神が宿る」というアニミズム的な考え方は、たしかに日本で広く見られますが、けっして日本独自のものではありません。語源であるアニマもラテン語から来ています。インドでも神は無数にいますし、自然物や、あるいは人工的なものであっても、礼拝の対象になります。このような考え方と仏教美術における象徴的な表現とは発想が違うのではないかと思います。
日本の夜叉は怖いイメージがあるけど、インドのヤクシャはそれほど恐ろしい感じがしないなぁと思いました。あと、28番目の写真では、ヤクシーを支えている人物がヤクシーより小さかったりして、人物の縮尺が一定していないのが不思議な感じでした。
日本の夜叉は般若のお面のようなイメージがありますが、これは日本独自の表現で、インドでは全く見られません。前回のスライドでは、ヤクシャをかなり紹介しましたが、これも仏教美術の重要な題材です。仏教美術を彩る多彩な登場人物とでも呼ぶことができます。初期の仏教美術をはじめ、今回紹介する南アジアのアマラヴァティーやナーガールジュナコンダ、あるいはアジャンタやエローラなどの石窟寺院でも好まれて描かれました。密教の仏にも、その特徴が受け継がれていきます。このような存在として、ヤクシャの他にもナーガ(龍王)やマカラ(想像上の生き物で、海に棲む)などがいて、インドの仏教美術の魅力のひとつとなっています。作品の中の人物の縮尺や大きさが一定ではないことは、たしかにインドではよく見られます。その理由にはいろいろありますが、いずれにしても、写実性が重視されなかったことや、独自の表現方法があったことが考えられます。
ストゥーパ。広辞苑で「そとば」(卒塔婆)を調べると?塔、?供養追善のために墓に立てる上部を塔形にした細長い板と。「ストゥーパ」って聞いたときに「卒塔婆?」と変換されたのですが、いや形が違うだろうと思い返して、調べてみたら先端が塔の形だったのですね・・・。
驚きだったこと。釈迦が象や菩提樹や車輪(法輪か)など象徴で表されていること。理由を聞いたら納得ですが。たとえはわかりやすかったです。もっと驚きだったのは、右脇から生まれてきたってことです。どうやって!?痛そう!
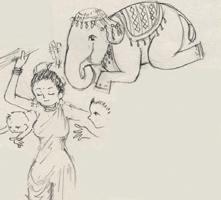 ストゥーパが卒塔婆の語源であることはそのとおりです。本来、ストゥーパはインドで作られた巨大な建造物で、仏教ではおもに仏の骨(「舎利」と呼ばれます)を収めるために作られました。写真でお見せしたように、半球形をしているのですが、中国や東南アジアなどではそれぞれ異なる形態の塔になりました。インドに比較的近いのは、ネパールやチベットの塔です。日本の五重塔や七重塔は、ストゥーパとはずいぶん形態が異なりますが、多宝塔と呼ばれる形態の塔は、ストゥーパに少し似ています。これらの仏塔については、もう少し先の授業で取り上げます。日本の墓地で用いられる板状の卒塔婆は、五輪塔と関係があります。五輪塔はその名の通り、五つの部分でできており、一番上に宝珠型(タマネギのような形)、その下に球や立方体などの石が積み重ねられています。これらは下から順に、地、水、火、風、空の五元素を表しています。人体を含め、すべての存在物はこれらの五つで構成されていると考えられ、人も死ぬと五元素に戻るため、墓として五輪塔が建てられます。卒塔婆の上の部分のでこぼこしたところは、五輪塔の形を簡略化して示したものです。
ストゥーパが卒塔婆の語源であることはそのとおりです。本来、ストゥーパはインドで作られた巨大な建造物で、仏教ではおもに仏の骨(「舎利」と呼ばれます)を収めるために作られました。写真でお見せしたように、半球形をしているのですが、中国や東南アジアなどではそれぞれ異なる形態の塔になりました。インドに比較的近いのは、ネパールやチベットの塔です。日本の五重塔や七重塔は、ストゥーパとはずいぶん形態が異なりますが、多宝塔と呼ばれる形態の塔は、ストゥーパに少し似ています。これらの仏塔については、もう少し先の授業で取り上げます。日本の墓地で用いられる板状の卒塔婆は、五輪塔と関係があります。五輪塔はその名の通り、五つの部分でできており、一番上に宝珠型(タマネギのような形)、その下に球や立方体などの石が積み重ねられています。これらは下から順に、地、水、火、風、空の五元素を表しています。人体を含め、すべての存在物はこれらの五つで構成されていると考えられ、人も死ぬと五元素に戻るため、墓として五輪塔が建てられます。卒塔婆の上の部分のでこぼこしたところは、五輪塔の形を簡略化して示したものです。釈迦の象徴的な表現は、古代の仏教美術のもつ最も重要な特徴であるとともに、宗教美術を考える上でもいろいろ示唆に富むため、強調しました。このような表現方法は、授業の本題である密教美術でも、実は重要な役割を果たします。最後の質問の「右脇から生まれる」ことの理由ははっきりわかりません。釈迦の超人的な特徴のひとつとして、古くから伝えられています。記憶が定かではありませんが、キリスト教やギリシャかローマの英雄などにも、右脇から生まれる伝説があるそうです。
初転法輪に向かう仏陀の像に、天使のような羽の生えた人が彫られていてびっくりしました。キリスト教やイスラム教のように「天使」って仏教にもあるんでしょうか。「イーをするヤクシャ」がとてもかわいくておもしろかったです。日本にもこういう面白味のある仏像ってあるんでしょうか。
このほかにも何人かの人から、天使についての指摘がありました。ガンダーラ美術はヘレニズム文化の影響を受けているので、西方世界のいろいろな要素が現れます。スライドではアポロンとダフネや、ハルポクラテースを紹介しました。羽の生えた童子は天使の姿に見えますが(森永のマークでもおなじみ)、それよりも古い起源を持ち、プットーと呼ばれます。弓矢を持つこともあり、この場合は愛の神となります。ガンダーラ彫刻ではプットーが好んで描かれ、装飾文様の中などにもしばしば現れます。この作品の場合は、法輪の左右から礼拝をしている姿をとっていますが、インドでは、同じような役割を神が行っています。このイメージは中央アジアから日本へも伝わり、飛天や天女の原型となります。
中学生の時、中国美術かインド美術家の像の浮彫を見たことがあるのですが、あれは酔象調伏の図だったのかと今発見しました。浮彫には丸い円の内にシーンを彫ってあるものがありますが、これは「法輪」をイメージしているのでしょうか。
授業ではまだ「酔象調伏」のスライドを紹介していませんが、配付資料でわかったのですね。名前も意味もわからないまま、イメージだけ記憶に残っているという作品が誰にでもあると思いますが、そういうものの再発見があるのはいいことですね。円形の区画はストゥーパの欄順装飾で好まれた形式で、バールフットやサーンチーをはじめ、インド各地で見られます。法輪も円ですが、実際は関係はないようです。円形区画をそのまま法輪として表現することがないからです。円という形そのものが好まれたようで、この中に釈迦の生涯の出来事などを巧みに表現しているところがひとつの見所です。物語を表す場合にしばしば見られる異時同景図、つまり複数のシーンをひとつの画面に収める手法も、そのひとつです。
教科書にあった事柄が出てきたので、ゴールデンウィーク中に読んでおいてよかったと思った。
授業は一応、予備知識なしでも理解できるように準備していますが、教科書であつかったことが随所に出てきますので、読んでから講義を聴く方が確実によりよく理解できます。大学の授業は出席する皆さんのそれぞれの自覚に任せられていますが、「〜することが望ましい」とか「〜しなければならない」と指示されたことは、もちろんやった方がやらないよりずっといいです。
インドは中国と違い、文献として記録することが少ないと聞きました。歴史と伝説とが混在してしまっているようなインドにおいて、今日スライドで映写された仏教美術作品は考古学的にいろいろなことを語ってくれる、とても貴重なものであると感心しました。美術と歴史はそれぞれ独立して関連性を持たないものだと思っていましたが、関連性のあるものだとわかりました。
たしかにインドは「史料なき国」とも呼ばれ、徹底した記録主義の中国とは対照的です。しかし、仏教をはじめとする宗教関係の文献は、非常に古い時代から残っているので、これらも一種の歴史的史料として扱えます。仏教の経典の記述から、当時の人々の暮らしをうかがうこともできるのです。このほか、石に刻まれた銘文などもかなり残されています。考古学と美術とに密接な関係があるのはご指摘のとおりです。美術というと実際に絵を描いたり彫刻を作ったりする実技が連想されますが、授業で扱っているのは美術史という学問分野に関わります。美術史は高校までは歴史の中の文化のひとつとして学んだと思いますが、ひとつの学問として成り立っています。その対象は博物館や美術館に展示されているものだけではなく、仏像のように現地の遺跡に残されたものも含まれ、現地調査が必要になります。その場合、考古学者との共同作業もしばしば行われます。
「初期の」仏教美術という言葉を用いておられましたが、仏教美術の時期区分の詳細はどのようになっているのでしょうか。
あまり意識せずに「初期」という言葉を使っていました。初期があれば中期や後期もありそうですが、実際は用いません。とくに釈迦をわれわれと同じような人間ではなく、象徴的な表現を取る時代を授業では「初期」と呼んでいます。具体的にはバールフットやサーンチーに代表されます。仏像が誕生したガンダーラやマトゥラーはその後の時代になります。南インドのアマラヴァティーなどは仏像と象徴的な表現が混在するので、少し状況は異なりますが、初期ではありません。その後は、インドの仏教美術の完成期とも言えるグプタ時代があります。具体的にはアジャンタ、エローラなどの西インドの石窟寺院や、サールナートを中心としたガンジス流域などが中心になります。授業のテーマである密教美術は、それに続くパーラ朝の時代に流行し、おもに東北インドがその舞台となります。